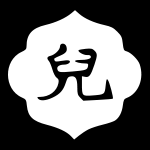|
宇喜多氏の本貫は備前児島で本姓は三宅氏といわれている。宇喜多諸氏の名が史料に見えるのは応仁・文明の頃で、宗家・宝昌・久家が存在し、
この頃、赤松氏の守護代浦上氏の被官として備前邑久郡豊原庄内にに蟠踞していた。
勢力を持ってくるのは久家の子能家の時で、備前守護代浦上宗助、その子村宗の有力な武将であった。
大永二年(1521年)村宗が赤松義村を討つにあたって功があったが、村宗の死後、天文三年(1534年)、邑久郡砥石城で浦上の将島村豊後守に謀殺された。
能家の子興家と、興家の子直家とは一時、備前国福岡に潜居していたが、やがて直家は同十二年、浦上宗景に従い各地に転戦した。
永禄二年(1599年)、上道郡沼城を拠点として、同十年備前明善寺で三村元親を盟主とする備中国人の連合軍を破り、
翌年、備前最強の国人松田氏を金川城に滅ぼした。天正元年(1573年)沼城から岡山城に移り、同五年、浦上宗景を和気郡天神山城に破った。
その前後、美作の三浦・後藤両氏を滅ぼした。直家は、初め毛利氏と連合して織田・羽柴勢に当たっていたが、同七年羽柴方と結び、毛利氏と対立するようになった。
同九年二月岡山城で病死。直家のこ秀家は、同十年の備中高城攻めの後、備中東半分、備前・美作二ヵ国、計五十五万国を秀吉から与えられ、
同十五年参議。文禄三年(1594年)権中納言に進み、その間文禄・慶長の役に従事した。
岡山城や城下町の整備、干拓など領国経営を行った。同三年大老。関ヶ原の戦いでは西軍につき破れ、豊後十一年八丈島に流罪となり、宇喜多氏は滅亡した。
|